【100円ショップ】陳列の基本
商品の陳列は商品を探すお客さんから見て、見やすくてわかりやすい陳列にするべきなのは当然だと思いますが、個人的に気をつけていたポイントに絞ってみていこうと思います。
陳列の基本的な考え方は適材適所だと思っています。
売れる商品は目立つところに、目立ちにくいところには売れない商品を陳列することでお客さんにもスタッフにも優しい売り場になると思います。
まず最初に、商品陳列を考える前に、ゴールデンゾーンという言葉を知っておく必要があると思いますので、簡単に説明します。
目次
ゴールデンゾーン
ゴールデンゾーンというのは床から75cm~135cmくらいの高さの範囲のことで、そこに陳列された商品がもっともお客さんの目に付きやすく、売れやすいと言われています。
たいていはお店側が一番売りたい商品をこのゴールデンゾーンに陳列していると思います。
では、本題の陳列に入っていきましょう。
商品の大きさ・長さ
まずは、陳列する商品の大きさや長さを見てみましょう。
各ジャンルに大きいものから小さいもの、長いものから短いものまで様々あると思いますが、仮にその中で一番小さい商品を最下段の足元に陳列してみるとどうなるでしょう?
おそらくほとんどのお客さんはその足元の小さい商品の存在に気付くことはないでしょう。
その商品に気付かないということは、その商品を知ったり、興味を持つ機会がないということなので、「買う予定じゃなかったけど良いものがあったから買っちゃった。」という100円ショップでよくある売れるパターンを外してしまうことになります。
また仮にお客さんがその商品を買いたいと思っていたとしても見つけられなければこの店では扱っていないと判断されてそのまま退店してしまうこともありえます。
これらは機会損失となり、お店の売り上げを落としてしまうことになるので気をつけたいです。
陳列棚の最下段というのは上記のゴールデンゾーンから遠く、ストックに使われることすらある非常に目立ちにくいエリアになります。
そんな最下段には、小さくて見つけにくい商品ではなく、大きくて長い比較的目立ちやすい商品を陳列するべきだと思います。
小さい商品は目線に近い高さに陳列してあげるとお客さんにも気付いてもらいやすくなります。
また、小さい商品でも入数が多く外箱のまま陳列するような商品は、その箱が大きければ最下段でも目立たないということはそれほどないので、商品そのものの大きさではなく、陳列したときのコーナーに占める面積の広さを基準に考えましょう。
外箱がなくても複数列・複数段に同じ商品を並べる場合も同じように広い面積に陳列することになります。
商品の売れ具合
次に、商品を売れる速さで見ると【売れ筋】【定番】【死に筋】の3つ分けられると思いますが、この3つのレベルを基準に陳列のレイアウトを考えてみましょう。
売れ筋
売れ筋はよく売れる商品ですが、『よく売れる』ということはたいていの場合たくさんのお客さんが買い求めるということです。
たくさんのお客さんが買いにくる売れ筋の商品を、コーナー最下段の隅っこのようなまったく目立たない場所に陳列してしまうと、その商品を求めるお客さんがその商品を見つけられず機会損失になってしまったり、商品の場所を訊かれる回数がかなり増えて作業スピードが遅くなってしまいます。
売れ筋はお客さんが見つけやすいように、ゴールデンゾーンか、そこに比較的近い場所に陳列しましょう。
お客さんも見つけやすく、スタッフ側も商品案内の回数を減らせてみんなにメリットがありますので必ず守りましょう。
定番・死に筋
売れ筋に比べて売れる数が少ない定番や死に筋は、売れないものほどゴールデンゾーンから離れていくように陳列します。
しかし、早く売りさばいてしまいたい商品や、今までは売れていなかったけどこれから売れる・売り込んでいくという商品は売れ筋でなくてもゴールデンゾーンに陳列するという考え方もあります。
状況に応じて柔軟に陳列を考えていきましょう。
導線
今度はお客さんが通る経路(導線)も考慮してみましょう。
ここからは陳列というよりはレイアウトに関する話になると思います。
ここで注目するのはお客さんが進む方向とお客さんの人数です。
お客さんはみんな入り口からメイン通路を通ってお店の隅の方へと進んでいき、目的のものを見つけたら入り口に戻っていきます。
入り口・店頭(そこを通るお客さん:全員)
↓
店舗の壁面に向かっていくメイン通路(多い)
↓
店舗の壁面に向かっていく通路(普通)
↓
壁面(少ない)
↓
入り口に向かっていく通路(少ない)
↓
入り口に向かっていくメイン通路(多い)
↓
入り口・店頭(全員)
お客さんはこの道程の途中でも目当ての商品を見つけたら入り口に戻っていってしまうので、壁面に進んでいくほどお客さんが少なくなっていき、商品がお客さんの目に触れる機会が少なくなっていきます。
入り口・店頭
入り口のところはすべてのお客さんが通る一番熱いゾーンになるので、お店でそのときに一番売れる商品を陳列していると思います。
おそらくどの店舗も店頭を催事コーナーとして旬の季節商品などを陳列しているでしょう。
店舗の壁面に向かっていくメイン通路
入り口に次いでお客さんが多く通り、かなり目に付きやすいゾーンなので、この通路を壁面に向かって進んでいるときに目に入るコーナーは売れ筋の多い主力ジャンルにしていることが多いと思います。
ここには売れ筋をたくさん並べていきましょう。
店舗の壁面に向かっていく通路
ここまでやって来るお客さんは少しずつ少なくなっていきますので、メイン通路沿いの主力コーナーほどではない程度に稼動するコーナーが多いでしょう。
売れ筋や死に筋よりも定番商品がメインになるコーナーが良いと思います。
壁面
壁面まで来るお客さんは、お客さん全体からみればそれほど多くはないかもしれませんが、壁面で商品を探すということは目当ての商品がそこにあるということだと思うので、それほど導線を気にしなくてもいいと思います。
上で書いた商品の大きさ・長さ、売れ具合を考慮した陳列を心がけましょう。
入り口に向かっていく通路
壁面まで来てから入り口に戻っていくお客さんはかなり少なくなってしまうので、壁面から入り口に向かうときに目に入るコーナーはあまり売れない商品の多いコーナーが多いと思います。
お店の中で一番売りにくいコーナーになると思うので、死に筋の多いジャンルはここに陳列するといいでしょう。
売れ筋をここに陳列してしまうと機会損失や、商品案内が増えてしまうので気をつけましょう。
入り口に向かっていくメイン通路
目的の商品を見つけたお客さんのほとんどはメイン通路を通って入り口に向かいますので、メイン通路を入り口に向かって進むときに目に入るコーナーも売れ筋を中心としたジャンルのコーナーにするといいと思います。
『壁面に向かっていくメイン通路』に次いでお客さんの多いゾーンになるでしょう。
個人的に思いつくのは以上でしたが、意外と複雑でしたね。
これらの陳列のポイントを押さえていけばお客さんには買い物がしやすく、スタッフには仕事をしやすい売り場になると思いますので、陳列に気を配ってより良い売り場を作っていきましょう。
商品発注についてもまとめていますのでぜひご覧ください。
→【100円ショップ】売り切れさせない発注のやり方
アドセンス広告 336 x 280 レクタングル (大)
関連記事
-
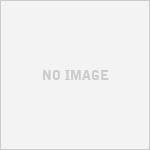
-
【100円ショップ】売り切れさせない発注のやり方
商品の欠品が大嫌いだった僕が、ダイソー系の100円ショップで働いていた経験をもとに、お客さんもより満
アドセンス広告 336 x 280 レクタングル (大)
- PREV
- 【100円ショップ】売り切れさせない発注のやり方
- NEXT
- 秋田弁まとめ
